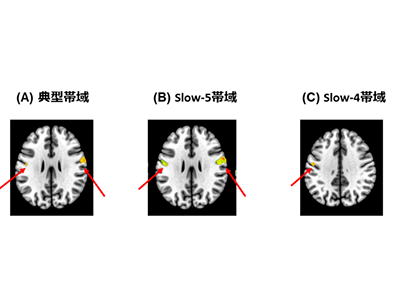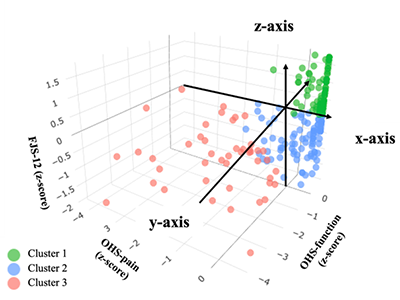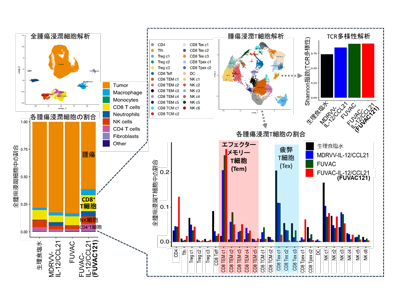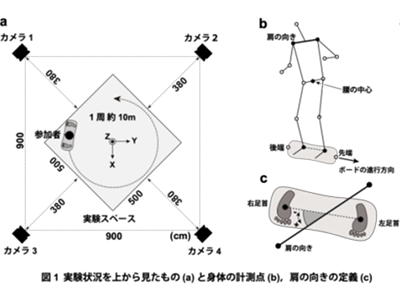分子標的治療ことはじめ
前門戸:私は自治医科大学の卒業で、9年間の義務年限を出身地の青森で勤めました。「研究は自分には必要ない、違う世界のものだ」と思っていたのですが、貫和敏博先生(当時 東北大学加齢医学研究所腫瘍制御研究部門呼吸器腫瘍研究分野教授)の教室の皆さまとの出会いもあり、義務年限後は大学院で研究を行うことになりました。研究を始めてすぐの1999年、貫和先生が「すごい先生を連れて来るよ」といって教室に迎えたのが、当時NIHで世界の第一線の研究をされていた萩原先生でしたね。

萩原:貫和先生は早くから遺伝子の取り扱いや分子生物学に興味をもち、ご自身もNIHでα1-アンチトリプシン欠損症の研究をされてから日本に戻り、東北大学に教室を構えていました。分子生物学を呼吸器領域に持ち込むことを目標に、若手を教育できる人材を探すなかで、留学中の私に声をかけてくださったようです。
貫和先生の慧眼には驚かされるばかりで、分子生物学的な“解析”が普及するかしないかのタイミングで、すでに「これからは治療介入が大事だ」と先を見据え、実際に取り組んでいました。「遺伝子で治療する」研究などほぼ誰も行っていないような時期に、現場で携われたわれわれは幸運でしたし、やりがいがありましたね。
前門戸:私の研究課題がまさに、がんの遺伝子治療についてでした。がん細胞でのみ複製するアデノウイルスに肺がん特異的なプロモーターを組み込んだ遺伝子治療の研究を主にマウス実験で行っていました。実際にがん抑制遺伝子p53遺伝子治療の患者投与にも携わらせてもらいました。
萩原:c-srcの発見は1979年1で、K-rasが脚光を浴びたのは1983年2。発見から時間が経つなかで“がん遺伝子”は治療標的にはならないと考えられ、“がん抑制遺伝子”が重要視されていた時代でしたね。EGFRもほとんど研究されていない、「おもしろくない遺伝子」という扱いでした。
前門戸:そのなかで2002年、EGFR-TKI(上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害剤)であるゲフィチニブが、NSCLCを適応に世界に先駆けて本邦で上市されました。女性・非喫煙などの効果予測因子が報告される3なか、2004年、NEJM誌4とScience誌5に、ゲフィチニブが奏効する患者さんにおけるEGFR遺伝子変異の発見がセンセーショナルに報告されました。
遺伝子の取り扱いに親和性のあったわれわれは、すぐに「自分たちもEGFR変異を測ってみよう」という話になりましたね。
萩原:ちょうどその1カ月後くらいに学会に参加する予定があったのですが「講演を聞いている場合じゃないぞ」と、その時間をEGFR変異の検出法の設計に当てたことを懐かしく覚えています。
前門戸:そして始まったのが、現在NEJの代表理事を務める小林国彦先生が研究代表者のNEJ6001試験ですね。
萩原:NEJ001試験は高齢者およびPS不良のNSCLC患者さんに対する救済療法としてゲフィチニブを投与する第Ⅱ相試験でした。当時の常識としては「PSの悪い患者さんで研究するなんて」と批判も受けましたが、EGFR変異をもつ患者さんをしっかり個別化することで、PS≧3の患者さん22名のうち68%がPS≦1になるなどの結果を得て7、次の第Ⅲ相試験NEJ002へと繋がったのです。
前門戸:EGFR変異をもつNSCLC患者さんにゲフィチニブあるいはカルボプラチン・パクリタキセル治療を割り付けたランダム化比較試験NEJ002は、私にとって思い入れの深い研究です。当時、宮城県立がんセンターでは多くの臨床試験が実施されていましたが、病棟担当医は私を含めて2〜3人で、気管支鏡も自分で行う多忙さでした。そのなかでも「遺伝子変異を調べて適切な治療を行う」というNEJ002試験のコンセプトは、ひときわ大事に感じられたのです。埼玉医科大学に栄転されていた萩原先生宛に、深夜のコンビニから細胞診検体を発送するのが私の日課でした。チームの努力が成就し、結果がNEJM誌に載った8時の達成感はひとしおでしたね。
東北大学で起きた基礎と臨床の「融合」
前門戸:NEJ002試験を行った当時、「ゲフィチニブが効く人と効かない人がいるとしても、投与すれば結局わかるだろう。苦労して遺伝子変異を測る意味があるのか」という意見がありました。ゲフィチニブの薬剤性間質性肺炎の副作用が知られるようになる前は特にです。
萩原:おそらく“遺伝子”がとてもハードルの高いものだったのでしょうね。われわれは遺伝子変異を測る方が簡単だと思えましたし、その方向に向かって走ることができた。この違いこそ、基礎研究の素養の有無によるものなのかもしれません。
あるいは、まだ“臨床試験の枠組み”というものが確立されていなかったという時代背景も影響したのでしょう。
基礎研究では再現性が重視されます。誰が何度行っても同じ結果が出ることが、正しさを証明するわけです。一方で、臨床研究を何回も行うことはできません。少数例の試験で薬剤の有効性を証明する枠組みはやっとできはじめた頃で、一般的ではありませんでした。
前門戸:たしかに、これまで行ってきた小規模の第Ⅱ相試験と第Ⅲ相試験のNEJ002試験とでは、異なる枠組みが必要でした。国立がんセンター(当時)で研修を受けた井上彰先生が戻り、東北大学に臨床研究のノウハウを根づかせてくれたのが大きかったと思います。
萩原:現在では当たり前のように用いられる臨床研究の枠組み、すなわち人間の「こうであってほしい」という期待や間違い――バイアスやアーチファクトと言われるものですが――を統計学的に削ぎ落とし、確率の範囲に物事をおさめる手続きを知った時は、カルチャーショックでしたね。
前門戸:遺伝子の取り扱いをはじめとする基礎研究の素養と、臨床研究の素養。この2つが東北大学のわれわれの教室で、たまたま融合した。その結果としてEGFR変異に基づく個別化が前に進んだように思います。萩原先生、そして井上先生がいなければ成しえないことでした。
萩原:「融合」というのは印象的な言葉ですね。医師が「基礎研究を学ぶ」ということは、ただ知識や技術を身につけるだけでなく、「アイデアを表現する手段を得る」ということだと思うのです。臨床研究も同じで、表現手段です。たくさんの表現手段をもつと、何が起こるでしょうか。例えば自分の考えを音楽で表現する人、絵画で表現する人、いろいろな人がいますが、それらが融合するとアニメになるといったように、まったく新しいものが生まれますよね。医学も同じで、複数の表現手段――例えば基礎と臨床――が融合する時に、新しいものができる。われわれは東北大学で、その1つの現場に居合わせた、ということなのかもしれません。
遺伝子変異はソリッドな指標だが全てを説明できない
前門戸:その後、日本人の肺腺がんではEGFR変異(約53%)を筆頭に、KRAS変異(約10%)、ALK融合(約4%)、RET融合(約2%)、ROS1融合(約1%)などがドライバー変異として知られるようになりました9。肺がん全体でみるとドライバー未知の症例も多く残るなか、新たに見つかるものは0.1%の桁になってきており、今後、ゲノム解析から新しいドライバー遺伝子変異の発見が起こる可能性は低いと考えられています。
「EGFR変異がなぜ日本人に多いか」というような観点で本邦で行われたゲノムワイド関連解析(GWAS)からも、従来の報告で発見された4つの遺伝子に加え、HLAを含む2つの遺伝子座の関連が僅かに見出されるばかりでした10。
萩原:GWASが盛んに行われてわかったことは「ゲノムだけを調べてもこれ以上はよくわからない」ということでしたね。つまり、疾患には遺伝子変異1個で起こるものから、影響力の異なる変異が複数混ざって起こるもの、変異以外の要因も複雑に関わり合って起こるものまで、複数の段階があるということでしょう。いまわれわれが知っているのは最初の段階だけで、要因が2つになるとわからなくなってしまう。まして3つになると“三体問題11”のように解けないことがわかってるというレベルです。今後“未知のドライバー”を明らかにしていくためには、新しい概念が必要なのです。
前門戸:その概念が何かはまだわかりませんが、端緒を掴むのは「GWASのような既存の解析手法ではうまくいかない」と気づいている人であることは間違いありませんね。糖尿病のような多因子疾患のために開発された分析手法や成果を、がんに応用していくという発想も有効かもしれません。
萩原:ブレイクスルーが基礎研究から出てくるにしても、臨床研究から出てくるにしても、基礎と臨床の両方、言い換えれば分子から患者さんの表現型までを身近に感じられないと、複雑な要因によって起こる疾患の理解は難しいでしょう。
前門戸:治療選択の指標としてすでに用いられているドライバー変異と、今後出てくるであろうエピゲノム、トランスクリプトーム、プロテオームといった指標の“違い”を理解するうえでも、臨床医が基礎研究の素養を身につける重要性は高まっていそうですね。分析も解釈も、遺伝子のようにソリッドにはいかない難しさがあるからです。
例えば、すでに実臨床で活用されているPD-L1タンパク質の発現測定は、検体採取の時期や部位によって変動します。基礎研究に馴染みの薄い先生方ですと、このPD-L1発現の有無と、ドライバー遺伝子変異の有無とを同列で論じる場面が見受けられます。「前者は変動しうるものだ」と理解していることは、患者さんに適切な治療を提供するうえで今後ますます大切なのではないでしょうか。
より多くの患者さんに治療を届けるために
前門戸:既知のドライバー変異をいかに効率よく患者さんから検出するかも、基礎研究の成果を臨床に還元するうえでいま重要になっています。
そのための課題はまず1つ、いかに組織を採取するかです。米国の先進的な大学では、ロボット気管支鏡による検体採取が行われはじめています。また、鉗子ではアプローチできない部位に腫瘍があったり、リンパ節や縦隔の生検が必要だったりする場合に威力を発揮する、気管支鏡下の針生検の技術開発も進んできています。
もう1つの課題は、採取した組織からいかに診断するかです。AIを活用した病理画像診断のような方向性もありますが、われわれ呼吸器内科医にとって目下重要なのは、NGSを用いた検査の推進です。現在、分子標的治療のコンパニオン診断には、PCRまたはNGSを用いた検査が行われています。前者は比較的検体量が少なく済み、TAT12も短いのですが、 minor uncommonと言われるようなごくまれであるが治療効果が期待できる変異を検出することができません。後者であれば稀なドライバー変異を網羅的に検出可能ですが、必要な検体量が多く、状態の悪い患者さんなど実施の難しい場合があります。患者さんへの負担を極力少なく、かつ一人でも多くの命をつなぐには、微量検体で実施可能なNGS検査が望まれるわけです。
萩原:私が開発している多遺伝子検査試薬(Mutation Investigator using the Next-era Sequencer:MINtS)はまさにその発想によるものです。1%以上のがん細胞を含む細胞診検体からでも、感度・特異度0.99でドライバー遺伝子を網羅的に検出することを目指し、NEJ021試験として研究を進めてきました13。
前門戸:こうしたデバイスや診断技術の開発も、まさに基礎と臨床の橋渡し研究と言えますね。

前門戸:私は卒後ずっと東北におり、萩原先生も東北に縁が深いということで、忘れられないのは東日本大震災のことです。私は宮城県立がんセンターで被災したのですが、メールの返信もできずたくさんの方に安否を心配いただきました。病院でなんとかPCを立ち上げて書いた当時のメールを読み返してみると、ずいぶん悲観的になっていたようです。燃料の確保ができなければ数日後には病院の非常電源が切れる。患者さんには缶詰のような食事しか提供できず「先生、私は犬猫ではありません」と詰め寄られる。水を病院の屋上まで階段で運ぶ。極限の状況でdefensiveな戦いを強いられていました。
被災から3日後くらいにチームを組んで向かった沿岸部の診療所は、ショックで泣き叫ぶ患者さんで溢れかえっていました。診療所の壮絶な臨床に追い打ちをかけるように津波発生の知らせがあり――後で誤報とわかりましたが、患者さんを避難させたこともありました。
萩原:余震が続いていましたから、命がけだったのではないですか。
前門戸:おっしゃるとおりです。その時に感じたのは、患者さんはもちろんですが、未来ある若い先生方も避難させなければということ。最年長だった私と看護師の2人が残り、自衛隊と協力して患者さんの避難にあたりました。
そのようななか萩原先生は発災から1週間後には現地入りして、本当に必要な医療資源を提供くださったと聞いています。
萩原:COVID-19のパンデミックもそうでしたが、足りないものは時々刻々と変化するので、とにかく色々な手を打って1つでも役立てばいい、というような感覚でした。NEJSGからの義援金を受け、当時いた埼玉医科大学にあるだけの薬剤をかき集めて、レンタカーを借りて、緊急車両認定を受けて、燃料も積んで、真っ暗な東北自動車道を走っていきました。
前門戸:医師はそれなりに充足していた一方、メディカルスタッフが不足していることに気づき、体制を整えてくださったそうですね。
萩原:現地から埼玉県に緊急要請をFAXしたところ、公立病院などから多数の看護師を集めて派遣してくださって。無理としか思えないようなことでも、本気の願いは届くのだと思いました。
その後は「上着は借りられますが、下着だけは借りられません」という被災者の声を聞き、山盛りの下着を送ったりもしましたね。

前門戸:萩原先生の現地入りよりさらに後の時期だったと思いますが、私が女川に手伝いに向かった際に持っていったものは、燃料、ナースシューズ、そしてホットプレートとお好み焼きの具です。医師として出来ることは限られていましたが、せめて温かいものを食べて元気を出してほしい。そんな思いで、一生懸命お好み焼きをつくったことが思い出されます。
新しい医療の可能性は一人ひとりの中に
前門戸:ここまでの話から、基礎と臨床が融合するような風土の重要性に疑いはないと思いますが、今の若い先生方はそのような状況にないのではないかと、心配なところがあります。
萩原:医学部の一般的な教育課程は、基礎医学を学んでから臨床医学を学び、基礎研究を行うならその後でという流れになっていますが、臨床の過程が長いというか。
前門戸:卒業して研修医になって、専攻医になって、専門医を取る。その道のりが険しいですよね。
萩原:正直に言って、現状の専門医の認定要件はわれわれが全貌をわからないくらいに難しい印象です。
前門戸:ノルマが多いですよね。専門医の取得に集中せざるをえず、基礎研究どころではないでしょう。米国と違って専門医資格が報酬に直結するわけではありませんので、基礎研究を行いながらじっくり専門医を取得するような考え方もあってよいと思うのですが…。実際に日本専門医機構でも、専門医をとりながらうまく大学院で研究を行えるようなシステムをつくろうとしているようです。
萩原:臨床だけですと独自の世界に入り込んで先に進めなくなってしまうこともありますよね。研修後に基礎研究の世界に戻るのはとても大切なことだと思います。
もう1つ大切なのは、基礎研究を行った後、必ず臨床研究も行うことではないでしょうか。
前門戸:基礎研究だけで、その成果を臨床に還元できる時代ではなくなってきていますからね。
萩原:新しい医療は、それまでの常識がひっくり返るところにあります。先ほども述べたように、かつてEGFRは誰も見向きもしないような遺伝子でした。ALKに関しても、肺がんに融合遺伝子はないというのが定説でした。
前門戸:従来の技術(Gバンド法)では、徹底的に調べても見つからなかったからですよね。
萩原:常識を打ち破るには困難を伴いますが、1つ確実なことがあります。それは、基礎研究と臨床研究、さらには基礎研究のなかでも分子生物学だけでなく、細胞生物学や実験動物学など様々な素養を持つ人材が増えれば増えるほど、思いがけない発見の可能性が高くなるということです。一人でも多くの若い先生方に、自分の可能性を信じ、基礎と臨床の2つの表現力を融合させながら、活躍いただきたいと願っています。
(了)
インタビュー実施日・場所/2022年7月28日・マンダリンオリエンタル東京
- 萩原 弘一(はぎわら こういち)
インタビュー実施時/自治医科大学 内科学講座 呼吸器内科学部門 教授
現所属/自治医科大学 客員教授 -

1983年、東京大学医学部医学科卒業 国立神経センター疾病研究第一部 研究見習生。’84年、東京大学医学部附属病院第三内科 研修医 東京都養育院附属病院(現東京都老人医療センター) 研修医。’85年、東京都立駒込病院内科(呼吸器) 医員。’86年、東京大学医学部附属病院第三内科 医員。’91年、同 助手。’93年、アメリカ国立癌研究所 Visiting fellow。’98年、同 Visiting associate。’99年、東北大学加齢医学研究所呼吸器腫瘍研究分野 講師。2000年、東北大学医学部附属病院遺伝子・呼吸器内科 講師。’03年、埼玉医科大学呼吸器内科 教授。’15年、自治医科大学附属さいたま医療センター総合医学第1講座 教授。
’16年、自治医科大学内科学(呼吸器内科学) 教授
- 前門戸 任(まえもんど まこと)
インタビュー実施時/岩手医科大学医学部 内科学講座 呼吸器内科分野 教授
現所属/自治医科大学 内科学講座 呼吸器内科学部門 教授 -

1989年、自治医科大学卒業 青森県立中央病院 初期研修。’91年、自治医科大学卒後義務のため青森県内の病院・診療所にて勤務。’98年、東北大学大学院医学系研究科 入学。2002年、同 大学院卒業 東北大学病院遺伝子・呼吸器内科 医員。’02年、同 助教。’06年、同 講師 宮城県立がんセンター呼吸器科 主任医長。’09年、同 呼吸器内科 医療部長。’11年、東北大学大学院医学系研究科連携講座呼吸器科腫瘍学分野 客員教授(併任)。’17年、岩手医科大学内科学講座呼吸器・アレルギー・膠原病内科分野 教授。’18年、岩手医科大学臨床研究支援センター センター長(併任)。’21年、岩手医科大学内科学講座呼吸器内科 教授。
- 参考文献
-
- Oppermann H, et al:Proc Natl Acad Sci U S A, 76:1804-8, 1979
- Shimizu K, et al:Nature, 304:497-500, 1983 McGrath JP, et al:Nature, 304:501-6, 1983
- Miller VA, et al:J Clin Oncol, 22:1103-9, 2004
- Lynch TJ, et al:N Engl J Med, 350:2129-39, 2004
- Paez JG, et al:Science, 304:1497-500, 2004
- North East Japan Study Group(NEJSG)による試験。2004年、ゲフィチニブの臨床研究を目的に北海道臨床試験グループ(リージョン)、東北リージョン、日本医科大学リージョン、および、埼玉医科大学リージョンが結合して組織された
- Inoue A, et al:J Clin Oncol, 27:1394-400, 2009
- Maemondo M, et al:N Engl J Med, 362:2380-8, 2010
- Kohno T, et al:Cancer Sci, 107:713-20, 2016
- Shiraishi K, et al:Nat Commun, 7:12451, 2016
- 2つの天体の運動を完全に説明できる万有引力の理論であるが、3つの天体になると計算できなくなってしまう。この問題は「三体問題」と呼ばれ、名だたる科学者・数学者たちが挑戦してきた
- Turn-around-time 検査の実施から結果を患者さんに返すまでにかかる時間
- Inoue Y, et al:PLoS One, 12:e0176525, 2017