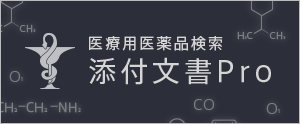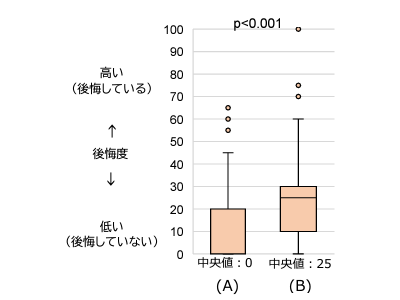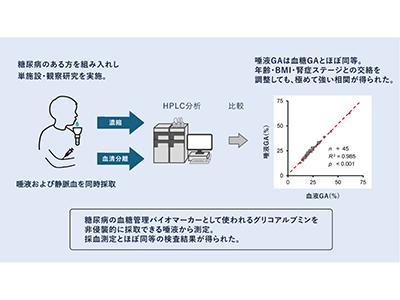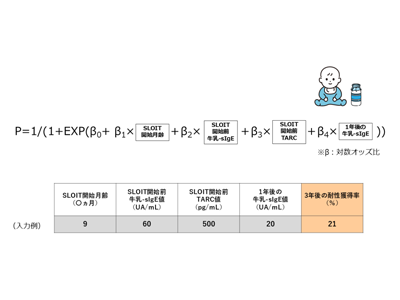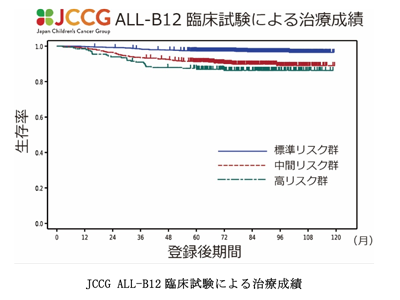5月20~23日に新潟市で開催された第56回日本神経学会学術大会。てんかんと就労の問題がテーマのシンポジウム「社会の中の神経学:はたらく人とてんかん」で、東北大学医学系研究科 てんかん学分野の柿坂庸介先生が小児から成人に成長する途中(ティーンエージャー)におけるてんかん診療の問題を主題に講演を行った。
■てんかんと共に成長する~患児に対する教育について~
柿坂庸介氏(東北大学医学系研究科 てんかん学分野)
「いつも親が決定する」患児の疎外感
最初に柿坂氏が注目したのは「医師と患児の関係性」である。海外調査によると、多くの患児が「治療の議論や方針決定が医師と親の間で行われている」ことに疎外感を感じている。柿坂氏は「幼少期は親-医師の関係で良いが、十代になってもこの関係が続いているのは良くない」と述べ、患児本人との意思共有が重要だと訴える。
さらに、親を介さないマンツーマンの診療は、患児の自尊感情の向上にもつながるという。「親たちは(私がいなくて)きちんと話せるのかと不安に思うが、患児たちはきちんと自分の考えを伝えることができる」(柿坂氏)
過剰な罪悪感から過保護に至る例も
次に柿坂氏は「子供に病名をどう告知するか」という問題を挙げる。
親に対する告知は当然だが、子供にも診断名を知らせるべきか。柿坂氏が聞いた話では、医師が子供にてんかんであることを告げた途端、隣にいた親が怒り出した事例があったという。
これに対して柿坂氏は「親の偏見に対して子供は非常に敏感だ」と指摘。親の過剰な反応が、逆に子供の自尊心を低下させることもあると注意する。
てんかんの告知は、親自身も苦しめる。否認、怒り、恐怖、抑うつなどの感情が一時的に生じるのは正常な反応だが、子供に対する罪悪感から「過剰な活動制限・過保護」に至る例もある。こうなると、患児は「1人では何もできない大人」に育ちかねない。
親には言えないことも話してくれる
柿坂氏は「子供たちは親が思うほど弱くない」という。事実、国内の報告でも、病名告知を受けた小学生の約5割が「全く気にしない」と回答。別の調査でも、てんかんを告知された小児患者(平均年齢13歳)のうち7割弱が「告知を受けてよかった」と回答していた。
柿坂氏は、患児本人への告知の利点として、(1)服薬や治療に前向きになる(2)(医師との信頼関係ができて)両親にも言えない病歴・症状を聴取できる(3)結婚・妊娠や運転免許の取得など将来の準備ができる――を挙げる。
患児教育の方法には、MOSES(モーゼス)と呼ばれるてんかん患者教育プログラムがある。知識のみならず、問題解決能力の育成に特化したプログラムで、発作頻度の減少や副作用の軽減にも貢献したという報告もある。
学校での発作は「タブー視しないで」
さらに柿坂氏は、学校関係者に対するてんかん教育も重要だと訴える。
東北大学病院てんかん科は、一般教員を対象に、てんかんの基礎知識、発作時の対応、日常生活における問題などをテーマとした講座を開催。教育者に対する教育に力を入れている。
講座では、教員に対して「(発作に対して)慌てる必要はない」と説明する。発作を他の子供に見せないよう隔離するなどの措置も不要だとして、「発作をタブー視するのではなく、当然という態度で接してほしい」と解説する。
病気のある友人を実際に見て学ぶことは、人間性に関する学びの場ともなりうる。柿坂氏は「無知は最大の敵だ」と語り、てんかんに対する正しい知識の啓発の重要性を強調した。
※この記事は株式会社ライフ・サイエンス「MEDICAMENT NEWS」第2199号(2015年6月25日発行)掲載誌面をもとにQLifePro編集部で一部再構成したものです。