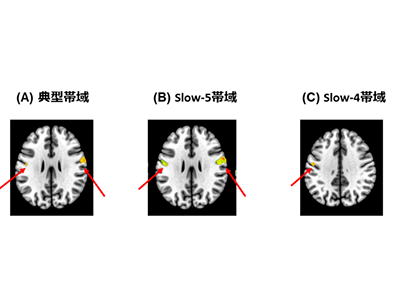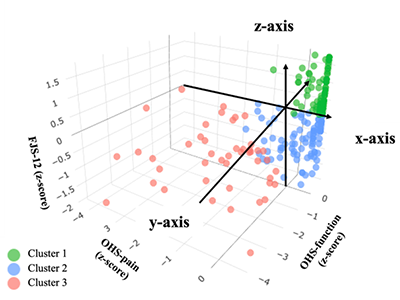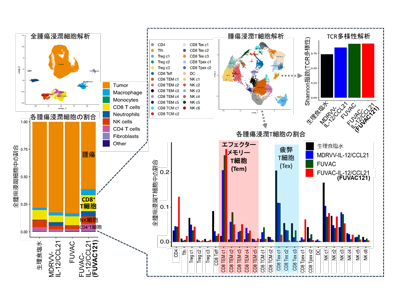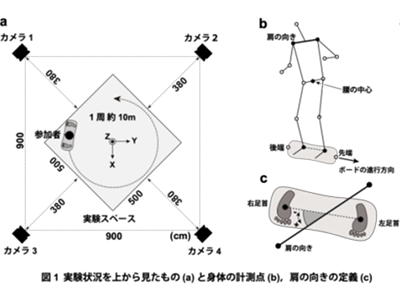全国てんかんセンター協議会総会(大会長:前原健寿氏:東京医科歯科大学脳神経外科教授)が2月14日、15日の2日間、東京医科歯科大学内にて開催された。期間中は各地のてんかんセンターからの現状報告、てんかん基礎講座、教育講演など多岐に渡る発表が行われた。
それらの講演の中から、シンポジウム2「てんかんセンターの現状と課題2」の概要を全4回に渡りお伝えする。今回は、国立病院機構西新潟中央病院小児科の遠山潤氏と、国立精神・神経医療研究センターの大槻泰介氏の講演を紹介する。
2015年2月15日:東京医科しい大学M&Dタワー(東京)
座長:亀山茂樹氏(国立病院機構西新潟中央病院 脳神経外科)
中里信和氏(東北大学大学院医学系研究科 てんかん学分野)
※この記事は株式会社ライフ・サイエンス「MEDICAMENT NEWS」第2193号(2015年4月25日発行)掲載誌面をもとにQLifePro編集部で一部再構成したものです。
遠方の難治患者を病診連携でカバー
国立病院機構西新潟中央病院小児科の遠山潤氏は「新潟県での小児てんかん診療連携の実際と課題~Dravet症候群症例を通して~」と題して、離れた地域に住む難治てんかん患児の治療と病診連携の実例を紹介した。
Dravet症候群は、乳幼児時期に発症する難治てんかんの代表例である。痙攣重積状態に至ることも少なくない。重積状態が長時間続くと脳に不可逆的変化が起きるため、重積時の対応は近医に頼らざるを得ない。遠山氏が紹介した事例は、いずれも西新潟中央病院でも治療を受けているが、普段は同院から離れた地域に住み、近医で治療管理を受けている患児たちである。
Dravet症候群は治療も難しいことで知られている。カルバマゼピンやフェニトインなど標準的治療薬では状態を悪化させることがある。痙攣を止めるためにホスフェニトイン静注をしたところ悪化した例もある。特殊な治療薬として臭化カリウムやスチリペントールを用いることもある。
遠山氏は実際の連携事例を挙げた上で「重積をきたす難治例をセンターのみで治療するのには限界がある」と指摘。治療方針を決定した後は、近医との連携構築が重要になると述べた。
てんかん2次診療施設の形成が急務
最後にコメンテーターを務める国立精神・神経医療研究センターの大槻泰介氏が、センターを中心とする連携体制の普及と今後について講演した。
中核施設を中心とする病診連携構想は、脳卒中領域やがん領域で実現している。てんかん領域も同様のはずだが明らかに他の領域より遅れている。原因の1つとして、大槻氏は「患者が声を上げづらい状況」があると指摘する。その上で「患者の声を代弁するのも拠点施設・全国てんかんセンター協議会の役割だろう」と訴える。
ではセンターが全国に普及した後はどうすべきか。大槻氏は、(1)てんかんについて学べる市民公開講座の開催(2)脳波判読の講習会(3)地域の2次診療施設の形成――などの役割を挙げる。
大槻氏は特に(3)を重視する。非専門医とセンターだけでは、百万人ともいわれるてんかん患者を診療することはできない。てんかん医療に通じた2次診療施設の協力がなければ、せっかくの拠点施設もパンクしてしまう。
大槻氏は、てんかんの地域診療連携拠点の整備事業など「重要なターニングポイントに来ている」と指摘。その上で医師一人ひとりが、これから3年5年の単位で連携を実現させるという強い意志を持つ必要があると訴えた。