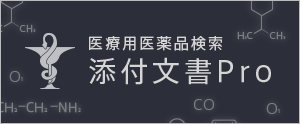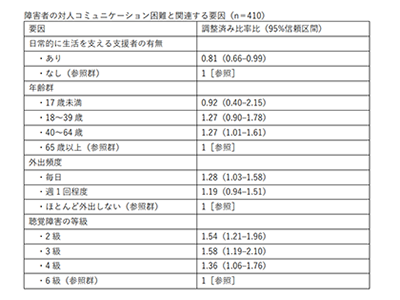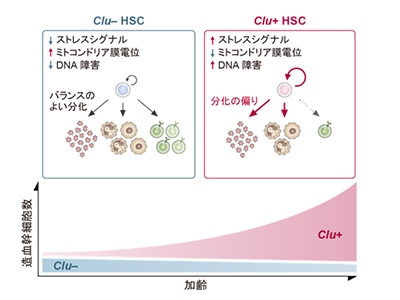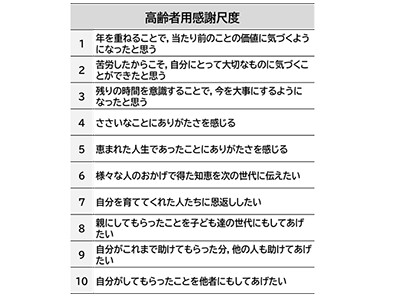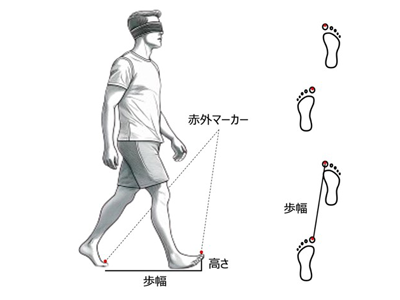■多くの患者が苦しむ血栓症

日本国内における脳血管疾患の患者数は、約140万人。そのうち「脳梗塞」患者が三分の二以上を占めている。また現在、エコノミークラス症候群として知られる肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症の患者数増加が注目されている。つまり、多くの国民が血液の凝固(=血栓)を原因とする病気に苦しんでいると言えるだろう。そしてそのような背景のもと、現在でも新たな薬の開発が進められている。
今回は、血液凝固機序から抗凝固薬開発の歴史、最近開発された新規抗凝固薬について、鈴鹿医療科学大学 薬学部 教授の鈴木宏治先生にお話しをうかがった。(本文中の画像はイメージです)
続きをご覧頂くには、QLife MEMBER IDによるログインが必要です。
QLife Member への登録がお済みでない方は、下記より会員登録をお願いいたします。
新規会員登録QLife MEMBER IDはQLifeが提供する様々なアプリやサービスを一つのIDで利用できる認証サービスです。
恐れ入りますが、本コンテンツの閲覧・利用は医師限定となっております。
医師であるにも関わらず本メッセージが表示されている場合は、プロフィール情報が間違っている可能性があります。
QLife MEMBERマイページにログイン後「医療者情報>医療資格」をご確認下さい。
■血液凝固因子トロンビンとXa因子の役割
凝固系は、外因系経路および内因系経路から始まり、X因子の活性化で合流、Xa因子、トロンビン、フィブリンの生成へと続きます。つまり、どちらの経路が活性化されてもXa因子の生成が重要です。Xa因子は凝固カスケードの「かなめ」といえるでしょう。
トロンビンの様々な生理作用
トロンビンには多彩な生理作用があります*4。傷害局所で大量に生成されるトロンビンはフィブリノゲンをフィブリンに変えて、XIII因子を活性化し、フィブリン塊を作らせます。また、VIII因子とV因子を活性化してカスケード凝固反応にポジティブフィードバックをかけ、凝固反応をより促進させます。さらに、トロンビンは細胞膜上のプロテアーゼ活性化受容体を活性化し、血小板血栓の形成を促すとともに、血管内皮細胞をはじめとする種々の細胞を活性化し、創傷治癒に必要な炎症や細胞増殖作用を示します。
その一方で、健常な状態の血管内にほんの微か生成されるトロンビンは、血管内皮細胞上のトロンボモデュリンに結合し、抗凝固因子のプロテインCを活性化します。そしてVIIIa因子とVa因子を不活化し、凝固反応を阻止して、血液の流動性を保つ役割を果たしています。
こうした正常時の作用とは別にして、鬱血や各種疾患による凝固亢進状態の血管内で生成されるトロンビンは、非限局的な病的血栓を形成し、深部静脈血栓症や肺塞栓症、脳塞栓症などの原因となります。
したがって、抗トロンビン薬によって、病態時に生成するトロンビンを直接阻害することは、病的なフィブリン血栓の形成や血小板の活性化を効果的に抑え、血液循環を正常に回復させることになります。
Xa因子の役割とXa因子阻害の意味
血液凝固カスケードは増幅反応であり、1つのXa因子から、多くのトロンビンが生成されます。つまり、大量に生成されたトロンビンを1つ1つ阻害するよりは、その上流においてXa因子を阻害した方が、より効率的に凝固反応を抑えることができると考えられます。
Xa因子は活性化血小板膜のリン脂質上でVa因子とプロトロンビナーゼ複合体を形成して、プロトロンビンをトロンビンに変換します。プロトロンビナーゼ複合体によるトロンビン生成の反応速度は、Xa因子単独に比較して30万倍にも及ぶことから*1、液相中の遊離型のXa因子を阻害するよりも、固相上のプロトロンビナーゼ複合体のXa因子を阻害した方がより効果的にトロンビンの生成を阻害できると考えられます。しかし、従来のヘパリン製剤やフォンダパリヌクスなどのアンチトロンビン依存性の抗凝固薬は、遊離型のXa因子を阻害できますが、アンチトロンビンが接近できないプロトロンビナーゼ複合体内のXa因子を阻害することはできません。
一方、アンチトロンビンに依存しない直接型のXa因子阻害薬は、遊離型のXa因子だけでなく、プロトロンビナーゼ複合体のXa因子も阻害できるため、より効果的に血栓形成を抑制できると考えられています。さらに、Xa因子阻害薬はトロンビンによる血小板活性化や細胞増殖作用を阻害しないため、止血や創傷治癒に影響を与えないとも考えられています。
また、Xa因子は組織細胞膜上のPAR-2を活性化して、血管組織の炎症や浮腫、血管拡張、血管内膜肥厚(動脈硬化)、口腔内の歯周病、腎炎などを誘発することが実験的に示されており、Xa因子を阻害することで、こうした炎症性病態を抑制できる可能性が考えられます。
■注射薬から経口抗凝固薬へ。抗凝固薬の開発の歴史
未分画ヘパリンは、血中のアンチトロンビンと結合し、凝固因子のXa因子とトロンビンを阻害して血液を固まりにくくします。1916年、この凝固阻害物質ヘパリンが発見されたことから、抗凝固薬開発の歴史は始まりました*1。ヘパリンに続いて、家畜のスィートクローバー病に端を発して開発されたワルファリンは、ビタミンK依存性の凝固因子であるプロトロンビン(II因子)、IX因子、VII因子、X因子の産生を阻害して血液を固まりにくくします。
その後、酵素や化学的処理で未分画ヘパリンを低分子量化した、低分子ヘパリンが開発されました。低分子量ヘパリンは、トロンビンよりもXa因子を相対的に強く阻害するため、血栓の抑制効果と出血増強作用を示す用量の乖離が大きくなり、治療域が広くなったことから、固定用量での投与が可能になりました。
1990年代には、特定の凝固因子を直接阻害する注射薬として、選択的トロンビン阻害薬のアルガトロバンが開発されました。現在もアルガトロバンは、慢性動脈閉塞症や脳血栓症、ヘパリン起因性血小板減少症などの治療で使用されています。

2000年代に入り、アンチトロンビンの活性化に必須である5糖構造(ペンタサッカライド)を化学合成した注射薬の、フォンダパリヌクスが開発されました。これは、アンチトロンビンによるXa因子阻害の選択性を更に高めたもので、間接型Xa阻害薬と呼ばれており、現在は静脈血栓塞栓症の予防や治療に広く用いられています。また、フォンダパリヌクスの登場によって、トロンビンを阻害しなくても、凝固カスケード上流のXa因子を阻害することによる、効果的な血栓症の予防・治療が実証されたといえます。
その後は、注射薬から経口抗凝固薬の時代に入り、プロドラッグであるキシメラガトランやダビガトランが開発されました。これらは直接型トロンビン阻害薬といわれています。キシメラガトランはその後、肝障害のため開発中止となりましたが、ダビガトランには認められず、下肢整形外科術後に起こる静脈血栓塞栓症の予防などに用いられるようになりました。日本でも「非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中および全身性塞栓症の発症抑制」の適応症で2011年1月に承認されています。
さらに、最近はプロドラッグ化なしの経口抗凝固薬として、直接型Xa阻害薬のリバーロキサバンなどが開発されました。これらの抗凝固薬は、心房細動患者における脳卒中予防におけるワルファリンとの比較試験の結果*2,3などから、現在注目を浴びています。また、脳卒中や静脈血栓塞栓症の予防だけではなく、静脈血栓塞栓症の治療や急性冠症候群の領域においても、新しい治療の選択肢として期待されています。
■新しい新規経口抗凝固薬のメリットと課題
経口吸収率の高いXa因子阻害薬を目指して
これまで開発されてきた合成の直接型Xa因子阻害薬には、DX-9065aやYM-60828があります。しかしこれらは、ヒトにおける経口吸収率が低く、医療現場で使用されることはありませんでした*1,5。そのため、経口吸収率が高いXa因子阻害薬の開発は重要な課題でした。
それまでは、開発されたトロンビンやXa因子を阻害する化合物は、アルギニン類似構造のグアニジノ基を有し、このグアニジノ基がトロンビンやXa因子の活性中心に直接結合して酵素活性を不活化すると考えられてきました。しかし、同時にこの親水性構造は体内吸収率低下の原因ともなっていました。
この状況を解消するため、Xa因子阻害活性と経口吸収の両方を満足させる、様々な化合物が探し出されました。その結果、リバーロキサバンやエドキサバンなどが開発され*1,6、現在、さまざまな血栓症の治療薬として、その有用性が研究されています。
出血リスクを最小限に抑える工夫が重要に
主作用と副作用の原因が同じ薬理である抗凝固薬のような薬剤は、相対的に安全域が狭く、また、薬剤の体内吸収率が一人一人で異なるため、至適投与量の設定は難しく大きな問題でした。こうした問題の解消するため開発された新しい経口抗凝固薬には、ワルファリンと比べていくつかのメリットがあります。
- ブリッジングが不要
- ルーチンのモニタリングが不要
- ターゲット以外の副作用のリスクが低い
- 食事制限がない
- 併用薬の制限が少ない
「モニタリングが不要で、固定用量で投与できる」ことは医師にとってメリットです。また、これまで他剤との相互作用や、食事制限を考慮する必要があったワルファリン投与患者にとっては、それらがなくなるメリットがあります。特に、心房細動性の血栓症予防のため、一生、抗凝固療法を続けなればならない患者にとっては、新規経口抗凝固薬はQOLの改善や服薬コンプライアンスの向上につながり、結果的に継続的な抗凝固療法を可能にするでしょう。
しかし、抗凝固薬であるからには、投与していないケースと比べ、出血リスクが増大することは間違いありません。とりわけ心房細動に起因する脳卒中予防は「予防医療」であるため、治療効果の恩恵よりも出血の副作用の方が注目されがちです。そのため患者や医師は、「血栓症予防/出血」、つまり、「ベネフィット/リスク」のバランスを認識することが容易ではありません。つまり、今後、新規経口抗凝固薬の使用が広がっていくためには、脳卒中などの血栓症発症リスクと出血リスクの適切な評価と、出血リスクを最小限に抑える工夫が一層重要になると思われます。
■最後に
どの経口抗凝固薬を選ぶかは、エビデンスなどの薬物プロフィールは重要ですが、患者からすると、コンプライアンス、出血以外の副作用、薬剤費なども考慮されるべき点です。これまでは、「どの患者に抗凝固療法を行うか」という選択に迫られていましたが、今後は「どの抗凝固薬を使用するか」という選択を迫られる時代が来るといえるでしょう。
(2) Connolly SJ, et al., N Engl J Med. 2009; 361: 1139-1151
(3) http://sciencenews.myamericanheart.org/pdfs/ROCKET_AF_pslides.pdf
(4) Ansell J., J Thromb Haemost 2007; 5 (Suppl. 1): 60-64
(5) Fujii, Y. et al., Drug Metab. Pharmacokinet 2007; 22: 26-32
(6) Eriksson BI, et al., Drugs 2006; 66: 1411-1429
(内容は2011年5月時点のものです)
鈴鹿医療科学大学薬学部教授、三重大学名誉教授、(社)日本血栓止血学会理事、(公)先進医薬研究振興財団理事、みえメディカルバレー企画推進会議会長、他。