今も原因不明のコロナ後遺症、治療方法は確立されていない
関西医科大学は3月31日、コロナ後遺症と全身性エリテマトーデスの類似性を示した研究結果を発表した。この研究は、同大大学院医学研究科イノベーション再生医学の服部文幸研究教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「International Immunology」に掲載されている。
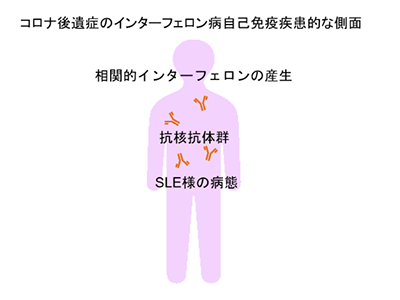
画像はリリースより
(詳細は▼関連リンクからご確認ください)
新型コロナウイルス感染症に罹患した患者のうち約2割が、完治後も体のだるさや呼吸困難感、集中力の低下、脱毛、味覚嗅覚障害、痺れなどの症状により、数か月から1年以上の長期にわたって苦しめられている。このコロナ後遺症は、パンデミックが終息した現在でも世界中の人々をコロナ前の日常生活から遠ざける大きな要因となっている。コロナ後遺症の原因については不明であり、確固とした治療方法も見いだされていない状況だ。
コロナ後遺症患者血清で複数のインターフェロン間に正の相関
今回の研究では、総合診療科コロナ後遺症外来受診者から世界保健機関(WHO)のコロナ後遺症診断ガイドラインに合致する患者を選択し、インフォームドコンセントに基づき39人分の血液サンプルを収集した。血清は同大バイオバンクセンターに寄託され、匿名化された。
バイオバンクから受け取った血清中のインターフェロンα2、β、γ、λ1、λ2/3の存在量をMultiplex Elisa法(同一反応で2種類以上のタンパク質を特異的に定量する方法)で測定した。各種インターフェロンの相関関係を調べたところ、多くの組み合わせで正の相関が見られた。さらに、性別と年齢の交絡因子を調整すると、すべてのインターフェロンに正の相関関係が見られた。
次に、血清に機能的なインターフェロンが含まれていることを示すために、各血清を細胞に暴露し、インターフェロンの刺激により発現誘導される遺伝子群のmRNA量を調査した。その結果、Mx1遺伝子の発現量が各血清中のすべてのインターフェロン量を示す値と正の相関を示した。
コロナ後遺症患者の血液単核球、SLE病態関与の遺伝子含めた免疫関連遺伝子の発現が変動
インターフェロンが中心となって病態形成を行う自己免疫疾患群をインターフェロン病(Interferonopathy)と呼び、その中の一つに指定難病である全身性エリテマトーデス(SLE)がある。そこで、コロナ後遺症患者と健常者の血液単核球の網羅的遺伝子発現情報を公共データベースから引用し、メタ解析を実施した。その結果、コロナ後遺症患者では、主に免疫に関わる遺伝子の発現が変化しており、SLEの病態に関与する遺伝子の一部にも変動が見られた。
コロナ後遺症患者の血液からSLEマーカーである抗核抗体群を検出、症状とも関連
SLEとコロナ後遺症は症状にも一部類似性があることから、コロナ後遺症患者血清に対し、SLEの診断に重要な抗核抗体群(抗DNA抗体および抗Sm抗体)の量を測定したところ、全ての血清が少なくともどちらかの抗体を含んでいることがわかった。性別と年齢の交絡因子を調整すると、抗DNA抗体と抗Sm抗体は、多くのインターフェロンに相関を示した。これらの結果から、コロナ後遺症患者には、インターフェロン病、特にSLEに類した病態要因が含まれている可能性が示唆された。
最後に、重回帰分析という統計手法で抗核抗体と症状の関連性を調査したところ、抗DNA抗体量は咳、鬱、脱毛、無嗅覚、筋・関節痛、抗Sm抗体量は熱、不整脈、無味覚との関連が見られた。
SLEの治療薬がコロナ後遺症の治療に役立つ可能性
今回の研究から、コロナ後遺症患者の血液に活性のあるインターフェロンが含まれており、さらにSLEの診断マーカーである抗DNA抗体、抗Sm抗体も存在することが明らかになった。各々の因子は患者ごとに一定の相関性を持って存在している可能性があることから、抗DNA抗体や抗Sm抗体を測定することが、コロナ後遺症の確定的な診断の手助けになる可能性が示唆された。
「今回の研究で、SLEに対する治療薬群がコロナ後遺症の治療に応用できる可能性が見えてきた。中でも、強化された自然免疫を弱めるとの報告があるヒドロキシクロロキンに注目している」と、研究グループは述べている。
▼関連リンク
・関西医科大学 プレスリリース




