近年増している「男性不妊症の検査や治療の重要性」
東北大学は11月17日、精子と精子の間に働く流体相互作用の解析を行い、精子が互いに助け合って泳ぐ、協調遊泳の効果を明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院工学研究科生体流体力学分野の大森俊宏助教、石川拓司教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Physics of Fluids」に掲載されている。
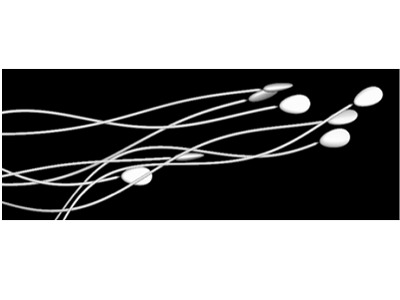
画像はリリースより
不妊に悩むカップルの約50%は男性側に原因があり、男性由来の不妊(男性不妊症)の検査、治療の重要性が近年増してきている。男性不妊の原因はさまざまあるが、精子の数が少ない事で不妊につながる乏精子症がある。乏精子症の状態では、運動性は良好でも精子数が少ないことで受精の確率が減るものと考えられているが、今回、研究グループは、精子の数が精子の運動性にも影響を与えることを明らかにした。
精子数が少なくても協調遊泳効果で精子運動を高められる
研究グループは、運動する精子と精子の間に働く流体相互作用を、力学法則に基づくシミュレーションによって解析。その結果、精子が集団化することで遊泳速度、効率が高まる協調遊泳の効果を明らかにした。精子が泳ぐことで作られる「液体の流れ」が、他の精子の運動を後押しする形となり、精子が多数いる時の方が早く、効率的に泳げることが判明。精子は受精を達成するために、体長の約3,000倍もの距離を泳ぐ必要があり、このような協調遊泳の効果は、長距離を早く確実に泳ぎ切るのに重要で、受精を達成する自然のメカニズムを表しているという。
これらの結果は、精子数が少ない状態でも密度が高まれば得られる効果であり、運動性が良好で数が少ない乏精子症患者の精液でも、通常の精子運動の状態へと引き上げられる可能性がある。研究グループは、「協調遊泳を利用して精子運動を高めることで、男性不妊に対する治療の効果が期待できる」と、述べている。
▼関連リンク
・東北大学 プレスリリース




