未就学児93人を対象に総合的に評価
米スタンフォード大学は7月21日、ADHD症状がある未就学児の79%が小学校生活への適応に不安要素を抱えていることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大医学部小児科発達行動学Hannah Perrin 研究員(当時)、同大医学部小児科のIrene Loe准教授らによるもの。この研究成果は、「Pediatrics」のオンライン版に 7月21日付で公開された。
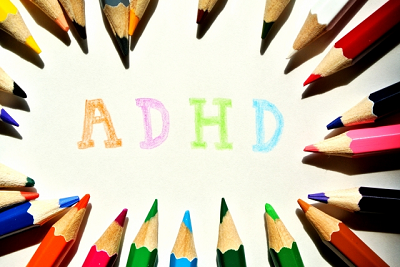
※写真はイメージ
ADHD(注意欠如・多動性障害)症状の特徴は、不注意や多動性、衝動的な行動がある。幼児なら誰にあっても不思議ではないため、就学前に発見することが難しいとされる。幼児の多くは、実際に学校環境で多くの問題を抱えるようになるまで、ADHDとは識別されない。学童期のADHD児の学業上の問題に関する研究はいくつかあったものの、就学前の幼児について調べた研究はほとんどなかった。そこで今回の研究では、未就学ADHDの幼児の学校生活への適応について総合的に調査した。
研究グループは、4~5歳の93人の幼児を対象に調査。48人はADHD症状がない幼児群、残り45人は、ADHD症状のある、または両親が有意なレベルでADHD症状があると認めた幼児群だ。ほぼ全員がプレスクールまたはキンダーガーテンに通っていた。すべての幼児を調査してADHD症状のレベルを確認した。
5つの項目を測定するため、対象児童の親に対してアンケートを実施した。項目は次の通り、「健康状態・運動機能発達」「感情および社会性の発達」「学習への取り組み」「言語発達」「一般知識および認知力」。「学習への取り組み」は、優先行動や課題を理解し、長期的な目標達成のために自制心を働かせて実行する能力があるかという評価を含んでいた。同年代の幼児と比べて、1つの項目で標準偏差が1以上悪いならば機能障害があり、2つ以上の項目で機能障害と判定された場合には就学準備が不十分とみなした。結果、ADHD幼児の79%で就学準備は不十分とわかった。一方、ADHDではない幼児では13%だった。
5項目中4項目において不安要素があると判明
「一般知識および認知力」の分野では、ADHDの幼児群と対照群との間に差は見られなかった。この分野は、文字・数字・形・色の識別、IQを含む、幼稚園入園ごろまでに形成されると考えられてきた重要な部分だ。一方、他の4つの分野すべてにおいて、ADHDの幼児は、対照群と比べて障害を来している可能性が認められた。「学習への取り組み」においては73倍、「感情および社会性の発達」は7倍、「言語発達」は6倍、「健康状態・運動機能発達」は3倍の差がみられた。
「この調査結果により、重度のADHD症状がみられる未就学児を特定し、支援することで、小学校入学後の問題を未然に防げるようになる可能性がある」と、研究グループは述べている。
▼関連リンク
・スタンフォード大学 News Center




