国内の40歳以上の有病率5.0%
緑内障・高眼圧症治療薬「ミケルナ(R)配合点眼液」(一般名:カルテオロール塩酸塩、ラタノプロスト)が1月11日に発売されたことを受け、大塚製薬株式会社が1月13日、都内でプレスセミナーを開催。「視野を失わないための緑内障治療の最前線」と題して、岐阜大学医学部眼科学教室教授の山本哲也氏が講演した。
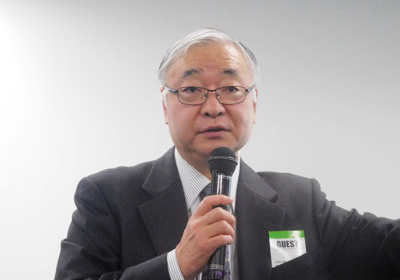
岐阜大学医学部 眼科学教室 教授 山本哲也氏
日本における失明原因の第1位である緑内障(厚生労働省研究班の調査より)。2007~2010年に視覚障害認定を受けた原因疾患でも、緑内障は21.0%で1位だ。日本緑内障学会が実施した大規模調査「多治見スタディ」では、40歳以上の日本人における緑内障有病率は5.0%だったが、有病率は年齢とともに上昇するため、高齢化の進展に伴い、今後も患者数の増加が見込まれている。現時点では決定的な治療法がないため、眼圧を下降させる治療を行い進行を遅らせる対症療法が中心だ。そのため、長期の視力予後改善には、早期発見、早期治療が重要になる。
日本における緑内障患者は、眼圧が21mmHg以下の正常眼圧緑内障が多いという山本氏。このため、健診などでの眼圧測定だけでは緑内障かどうかがわからない。さらに、発症早期には知覚できる視野の変化がわずかであるため早期発見が難しく、異常を自覚して眼科受診に至るころには、すでに病状が進行していることもあるという。
視野異常なく、画像診断で診断されるケースも
緑内障治療の薬剤選択にあたっては、眼圧下降効果はもちろん、副作用や利便性も考慮する。治療は原則として単剤で開始されるが、眼圧が十分に下降しない場合は複数の点眼液を使用することもあるといい、その場合でも点眼薬の数や点眼回数が少なく、充血などの副作用ができるだけ少ない薬剤を選択するという。慢性疾患である緑内障は生涯にわたり治療が必要になるため、長期にわたる有効性と安全性に加え、アドヒアランスがよいことが求められるが、2剤以上の併用例では、アドヒアランスが低下しやすい。そのため、配合点眼液のニーズが大きい。既存の配合点眼液は、β遮断薬としてチモロールマレイン酸塩を含有していたが、今回発売された「ミケルナ」ではβ遮断薬としてカルテオロールを配合。脈や血圧など全身への作用が既存薬とは異なるため、治療の新たな選択肢となるという。
「近年では、光干渉断層計(OCT)の普及により、視野異常が出ていなくても、画像診断で視神経に障害が見つかり緑内障と診断される例も出てきている。特に自覚症状が少ない初期症例や、アドヒアランス不良例、高齢者などでは、2剤併用よりも利便性の高い配合点眼液が適している」(山本氏)




