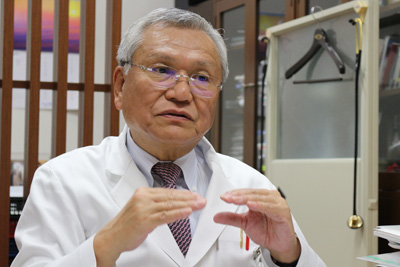3つの第3相試験結果がNEJMに掲載
ヤンセンファーマ株式会社は2016年11月17日、ウステキヌマブ(製品名:ステラーラ)のクローン病患者を対象とした第3相試験の成績が英医学誌「New England Journal of Medicine」に掲載されたと発表した。ウステキヌマブはヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤で、日本では尋常性乾癬および関節症性乾癬の治療薬として、2011年に承認を取得。2016年3月には中等症から重症の活動期にあるクローン病の適応追加を承認申請中である。
同剤の第3相試験は、2つの寛解導入試験(UNITI-1、UNITI-2)と、両試験でウステキヌマブ投与後にクリニカルレスポンスが得られた患者を対象とした寛解維持試験(IM-UNITI)の3試験で構成。UNITI-1試験は1回以上の抗TNF-α治療で効果不十分または忍容性のなかった患者が対象で、UNITI-2試験は抗TNF-α治療以外の既存治療で効果不十分であった患者が対象。その結果、UNITI-1試験ではウステキヌマブ130mg投与群の34%と同剤~6mg/kg投与群の34%で、主要評価項目である6週時のクリニカルレスポンスが得られた(130mg投与群:p=0.002、~6mg/kg投与群:p=0.003、vs. プラセボ)。UNITI-2試験では、同剤130mg投与群の52%と同剤~6mg/kg投与群の56%で、主要評価項目である6週時のクリニカルレスポンスが得られた(いずれもp<0.001、vs. プラセボ)。寛解維持試験では、同剤を8週毎投与群、12週毎投与群のそれぞれ53%、49%で、主要評価項目である44週時の臨床的寛解が得られたという(p<0.05、vs.プラセボ)。
有害事象については、UNITI-1試験では同剤130mg投与群、同剤~6mg/kg投与群、プラセボ群でそれぞれ65%、66%、65%に有害事象が発現。そのうち重篤な有害事象がそれぞれ5%、7%、6%にみられた。UNITI-2試験では、同剤130mg投与群、同剤~6mg/kg投与群、プラセボ群でそれぞれ50%、56%、54%に有害事象が発現。そのうち重篤な有害事象がそれぞれ5%、3%、6%にみられた。IM-UNITI試験では、同剤90mgを8週毎投与群・12週毎投与群・プラセボ群でそれぞれ82%、80%、84%に有害事象が発現。そのうち重篤な有害事象がそれぞれ10%、12%、15%にみられたという。
抗TNF-α治療の治療不成功例に対する次の選択肢に
今回、QLifePro編集部では、クローン病治療の第一人者でウステキヌマブの治験にも参加している、北里大学北里研究所病院炎症性腸疾患先進治療センターの日比紀文センター長を取材。同試験結果とクローン病治療の展望についてお話を伺った。
生物学的製剤の登場でクローン病の治療は大きく変わったという日比氏。それまでは、栄養療法、ステロイド、免疫抑制剤、5-ASA製剤による治療が行われていたが、完全寛解に至る例はほとんどなかった。そこへ、生物学的製剤をうまく使うことで、ある程度炎症をコントロールできるようになり、多くの患者が日常生活に復帰できるようになったという。しかしなお問題点も残っている。日本で現在クローン病に適応のある生物学的製剤は抗TNF-α抗体製剤のみであり、副作用出現時や無効例への対策が少ないのが現状である。薬価も高額で、バイオシミラーも安くはない。特に、抗TNF-α治療の一次無効例や二次無効例(failure)の存在も問題で、failureにはステロイドで治療を行うが、ブデソニドなど局所ステロイドの使用が可能になったとはいえ副作用が問題となるという。
日比氏によると、クローン病は炎症が強いためか、発症機序が異なるためか、他の自己免疫疾患ですでに使われている生物学的製剤でも、クローン病の治験では効果がはっきり出ないこともあるという。今回治験が行われたウステキヌマブは、プラセボを使ったダブルブラインドの試験で有効性が認められた。この結果をみて、日比氏はしっかりとした力を持った薬という印象を持ったという。今回の治験に参加した日本人患者には、抗TNF-α治療のfailureが含まれており、failureにおいてもウステキヌマブの有効性が示された。日比氏によると、これはウステキヌマブが抗TNF-α抗体とは違うサイトカイン(IL12/23)をターゲットにしているためとも考えられるという。抗TNF-α治療のfailureでも有効だった患者がいる、このことが与えるインパクトは大きい。生物学的製剤のスイッチが可能になるからだ。「クローン病治療では、抗TNF-α治療のSecondary failure(寛解維持の不成功例)で増量しても効果がみられない患者に対して、次に何をするのかが課題になっている。このような症例に対する次の選択肢として、ウステキヌマブが入ってくるだろう。または炎症によっては、ウステキヌマブを最初に使用することも出てくる。そうすれば、効果が出なかったり、治療がうまくいかなかったりする患者の数を減らしていけるかもしれない」(日比氏)
病態を考慮した治療薬選択で、炎症をコントロールできる時代に
今回の治験では、サブ解析で粘膜治癒についても評価予定。日比氏によると、クローン病の粘膜治癒については意見が分かれるところだという。粘膜治癒はSES-CDに基づき内視鏡所見で評価することが多いが、表層の粘膜だけに炎症が起こる潰瘍性大腸炎とは異なり、クローン病は全層性の炎症。内視鏡の所見だけで本当に粘膜治癒といえるのか、どこまで評価できるのかはわからないという。ただし、粘膜治癒例と粘膜治癒していない例では、粘膜治癒例のほうが炎症の抑え方が強く、粘膜治癒していない例は炎症を完全には抑えられていない。炎症をしっかり抑えていれば再燃が少なく、効果も持続することが期待できる。クローン病は慢性の炎症がずっと続く、いわばくすぶっている状態であり、消し炭のように炎症が残っているので、生物学的製剤の治療をやめるとまた悪くなる患者も多いが、粘膜治癒が起きていれば、そのくすぶりが小さいといえるという。
クローン病でもターゲットを絞った生物学的製剤がいくつか出てきており、今後はこうした生物学的製剤が治療のメインになっていくという日比氏。ウステキヌマブも、副作用の問題が出てこなければ、IBD治療におけるインフリキシマブやアダリムマブと同じような地位に入ってくる可能性が考えられる。クローン病では、ほかにもターゲットの異なるさまざまな薬剤の開発が進行中。ターゲットを絞った生物学的製剤が登場することで、有効なターゲットが明らかになれば、今度はそれらを標的とした低分子薬が出てくる可能性があるという。
患者ごとに病態が違うクローン病。一人ひとりの病態を考慮して治療薬を使い分けることで炎症をコントロールできるようになると日比氏。クローン病治療のゴールは患者がふつうの生活を送ることであり、入院して炎症を抑えることをゴールとする段階はすでに終わっているという。新たな薬剤の臨床経験が積み重なり、それぞれの薬剤の有効例、無効例が明らかになることで、病態の解明も進み、治療が進歩する。「新薬が出るということは、いわば武器が増えるということ。炎症という敵に対する武器をいっぱい持ち、その武器の性質や使い方を知る。患者さんに合わせて武器を選んで、それを適切に使用して、炎症をコントロールする。そうすれば、患者さんはふつうの生活に戻っていける」(日比氏)
▼関連リンク
・ヤンセンファーマ株式会社 プレスリリース