オミックス解析を用い、2010年の成果をベースに検証
東京医科歯科大学は9月21日、ハンチントン病の治療薬シーズのスクリーニングとそこから得られた化合物の構造情報解析を行い、有望な候補ペプチドを得て、その作用機序を明らかにしたと発表した。この研究は、同大学難治疾患研究所神経病理学分野の岡澤均教授、同分子構造情報学分野の伊倉貞吉准教授らの研究グループによるもの。研究成果は「Scientific Reports」オンライン版に9月22日付けで掲載されている。
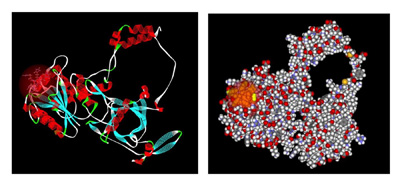
画像はリリースより
アルツハイマー病、パーキンソン病、ハンチントン病、脊髄小脳失調症、筋萎縮性側索硬化症などの神経変性疾患は、それぞれに特異的な疾患タンパクの脳内凝集が病理診断の基準となっている。一方で、病態にとっては、疾患タンパク質の凝集のみが意味があるのではなく、疾患タンパク質もしくは疾患RNAに起因する、多様な細胞機能の異常あるいは臓器間関係の異常が重要な意味をもっていることが、それぞれの疾患において明らかになっている。
岡澤教授らは、細胞サンプルや組織サンプルに含まれる多様な分子の状態を包括的・網羅的に解析する研究方法であるオミックス解析を用い、2010年に神経細胞において主要な役割を持つDNA損傷修復タンパク質Ku70が、ハンチントン病疾患タンパク質(変異型ハンチンチン)と結合して、その機能障害に至ることを明らかにしている。これをベースとして、今回の研究では、変異型ハンチンチンとKu70の結合を阻害する低分子化合物を得て治療薬シーズとすることを目的とし、1分子蛍光解析装置MF20によるin vitro結合阻害解析などを行い、候補化合物を取得。ハンチントン病のヒト患者由来のiPS細胞を用いて、これらの候補化合物の治療効果を検証したという。
他の治療方法と合わせた統合的治療への活用も
その結果、最も効果のあったのはヒスチジンというアミノ酸が7個連続したペプチド(7H)で、7Hは、Ku70と変異型ハンチンチンの異常な結合を抑制することも確認され、分子構造上、ある程度の共通性を持つことも分かった。さらに、動的光散乱法という技術を利用し、治療効果を持つペプチド3種類のハンチントン病の疾患タンパク質凝集に対する効果を検証したところ、凝集を阻害する効果はなかったものの、予想外に凝集過程(時間的な凝集スピードの変化)を変えて、最終的には凝集量を増やすことも明らかとなった。これに対応して、投与を受けたマウスの脳でも凝集体は変わっていないが、運動機能や体重などに治療効果が出ていたということも確認できた一方、7Hなどの候補薬シーズはDNA損傷などの病態を軽減していることも確認したとしている。
神経変性疾患における疾患タンパク質には大きく分けて、
(1)疾患タンパク質が凝集して細胞内外に蓄積することが毒性の原因であるとする古典的な考え方
(2)疾患タンパク質の立体構造(コンフォメーション)が変化した時点で毒性の獲得が始まり、モノマー、オリゴマー、あるいは中間体という凝集前の疾患タンパク質により強い毒性があるとの近年提唱された考え方
(3)その両者が正しいとする考え方
の3つの考え方があるが、今回の結果は、この中で(2)あるいは、少なくとも(3)の仮説を支持するもので、今後の神経変性疾患の治療戦略にも示唆を与えるものとなる。
近年、神経変性疾患のさまざまな治療法が実験段階で提案され、一部は臨床試験段階に進んでいるが、がんと同様に多様な治療法を合わせた統合的治療が必要となることが予想されている。今回の研究で得られた治療薬シーズは、他の治療方法と合わせてより良い治療法に結びつく可能性があると研究グループは述べており、今後、ペプチド医薬品の開発につながることが期待される。
▼関連リンク
・東京医科歯科大学 プレスリリース




