被告2人に損害賠償責任は認められないとの判断
2016年3月1日、列車衝突事故を起こした認知症患者の家族に対する損害賠償請求訴訟の上告審があり、最高裁は下級審の判決を不当として破棄し、被告2人に損害賠償責任は認められないとの判断をして確定した。各方面で大きな議論になっているが、QLifeProでは、認知症の方の見守りの一環として成年後見人制度の活用に取り組んでおられる大瀧靖峰弁護士(フロンティア法律事務所、東京弁護士会所属)にご意見を伺った。
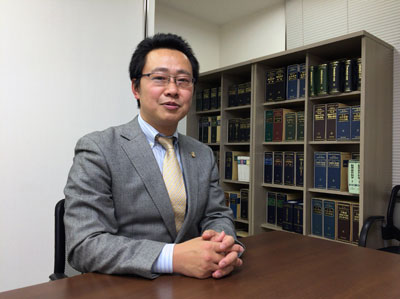
大瀧靖峰弁護士
(フロンティア法律事務所、東京弁護士会所属)
法曹界から見た注目すべき点は
QLifePro編集部(以下編集部):今回の判決が同種の訴訟の先例となるわけですが、法曹界から見た注目すべき点を。
大瀧弁護士(以下大瀧):論点としては、大きく2点です。1つ目は同居の配偶者、または長男が民法714条1項に規定されている「監督義務者」にあたるのかどうか、2つ目はまたそうでないとしても本件の被告らが準監督義務者(民法714条1項類推)にあたる事案だったのかどうかです。判決としては1つ目も2つ目も否定となりました。つまり、今回においては、被告となった2人は、事実としては介護をしていたわけですが、法律上は損害賠償の責任を負う立場ではない、という判断になったということですね。
編集部:つまり今後は、自宅で介護する家族は、基本的に損害賠償責任を負わないということでしょうか。
大瀧:いえ、そうではありません。今回は最高裁の判断としては、より正確に言うと「今回の被告の2人は監督義務者でも準監督義務者でもない」と事例判断をしただけなのです。
損害賠償責任を負う判断基準はあるのか
編集部:では、どういった場合に損害賠償責任を負う判断基準のようなものは示唆されていますか。
大瀧:判決文以外の補足意見、各意見にもさまざま見られますが、今回の被告はたまたま賠償義務を負わないというだけで、
という一応の基準は示しています。とは言っても、介護の状況に即してその都度判断するべきだ、ということに過ぎないのですが。
編集部:今回の場合「賠償責任を負うべき立場ではあったが、できる限りのことをしているし責任があるとは言えない」という判断をしても良かったのでは。
大瀧:判決文の最後に、
と書かれています。これがわざわざ入ったということは、裁判官の間でも、考え方が分かれたということですね。また、同居の妻だから、長男だからといった親族であることのみを理由にして「監督義務者」や準監督義務者にあたるとすることはできない、ともしています。この監督義務者、準監督義務者となる要件は相当に高いもので、いわゆる家族の扶養義務とはまったく異なるものです。
編集部:つまり、家族だから介護する義務があるというような話は、まったく根拠がないと。
大瀧:そうですね。認知症に限りませんが、日常的に看護やケアが必要な方を世話する行為は、扶養ではなく、したがって義務もありません。扶養は主に経済的な援助をしていること、生計を援助していることを指しますので。
細かいところはまさに今後それぞれの事例で判断するしかないという判決ですが、少なくとも分かったことのひとつは「家族だからといって、また自宅で介護する選択をしたからといって、直ちに損害賠償責任を負っているわけではない」ということでしょうか。
家族以外に責任を負うケースはあるのか
編集部:家族以外でこうした患者さんを見守る立場の「プロ」に責任が及ぶケースは出てくるでしょうか?
大瀧:判決文にも、成年後見人がいた場合の検討経過について書かれています。法律的に「身上配慮義務」というのが課されているので、これが損害賠償責任を問えるものかどうか、という議論ですね。こちらについては結論から言えば「身上配慮義務」は現実の介護や行動監督を指しているわけではないので、対象から外れると判決に明記されていますね。
編集部:すると、介護の実務を担う人は責任を問われうる?
大瀧:可能性はあります。家族と同じように、一律否定はされていない、と理解するのが妥当でしょう。介護をしているから自動的にということではなく、まさに判決文にあるように「責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるか否か」ということです。ただ、この表現の直前に「現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど衡平の見地から」とあります。
編集部:「可能かつ容易」というのは、何を指すと考えられますか。
大瀧:断定的には言えませんが、今回の事案に照らして考えると、徘徊や自傷他害行為を容易に防止することができる立場にあるものということになります。これはかなりハードルが高いと思います。施設だったらそれは可能ではないか?と思いがちですが、容易に防止できる措置や設備が認められている施設は、かなり重度の精神障害に対応する施設のみですし、実際に措置を講ずるにあたっても様々な要件の下での法的な手続きが必要になります。施設だからと言って、「可能かつ容易」というわけではありません。だから現実の介護に基づく訴訟リスクを極度に恐れて、認知症の人を施設に送ればいいというわけでもありません。そもそもそんな理由で施設に介護をお願いできません。
編集部:それは倫理的にもちょっと考えづらいですね。
最高裁の示したメッセージ
大瀧:判決文本文には入っていないものの、直後の補足意見の中にこういう一節があります。
この一節は補足意見ですので、判例として未来の判決を拘束するものではありません。が、しかし、この文を読む限り、介護現場で通常行われていること、ケアマネだったり成年後見人であったり、訪問介護であったり、自宅での介護に関わる人たちの業務イコール損害賠償責任がついているわけではないんです、ということを、わざわざ示してくれているんだと思います。
ただし、認知症の人の行動によって発生する各種の損害について、本人、家族、介護者、及び鉄道会社などの、特定の個人や法人に押し付けることになるようでは人々は認知症の人を避けるようになってしまいます。そのような状況となれば、認知症の人の人権が守られないだけでなく、皆が暮らし易い社会とは言えないと思います。社会全体のコストとして、包摂していく必要があります。
編集部:裁判官の方が、在宅介護の現場について本当によく見てくださっていることが分かりますね。また、認知症については、社会全体の問題として取り組んでいかなければならないことも分かりました。ありがとうございました。

■大瀧靖峰 弁護士(http://otaki-yasumine.kaisya.info)
フロンティア法律事務所
東京大学法学部卒、東京弁護士会所属
高齢者障害者の権利に関する特別委員会 副委員長
日本弁護士連合会 人権擁護委員会 障がい差別禁止法制特別部会 特別委嘱委員
経済産業省 中小企業経営革新等認定支援機関




