小脳疾患の病態解明や治療法の確立に
独立行政法人 国立精神・神経医療研究センターは3月6日、神経研究所病態生化学研究部の星野幹雄部長らの研究グループが、多様な神経細胞を生み分ける新たな仕組みを明らかにしたことを発表した。
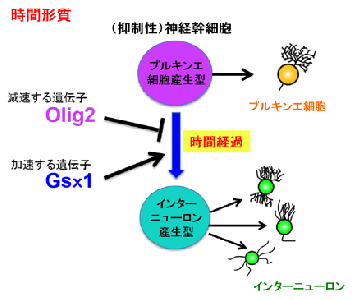
(画像はプレスリリースより)
プレスリリースでは
小脳機能異常が原因となる一部の運動失調や自閉症および認知障害などの、小脳疾患の病態解明や治療法の開発につながる社会的意義の高い研究成果です。(独立行政法人国立精神・神経医療研究センター プレスリリースより引用)
と述べられている。
神経幹細胞が時間形質で変化
研究グループは小脳を調べることにより、最初はプルキンエ細胞を生み出す性質を持っている脳室帯の神経幹細胞が、時間的経過の中で細胞分裂を繰り返すうちにインターニューロンを生み出す性質を持つものに変化することを明らかにしたという。
このような神経幹細胞が時間経過において変化させる性質のことは「時間形質」と名付けられた。
また、「Gsx1」と「Olig2」という2つの遺伝子が、神経幹細胞のプルキンエ細胞産生型からインターニューロン産生型へ変化する時間形質のスピードコントロールに関与していることも明らかにしたとしている。(小林 周)
▼外部リンク
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター プレスリリース
http://www.ncnp.go.jp/press/press_release140306.html




