TARM1が疾患に与える影響はよくわかっていなかった
東京理科大学は3月17日、免疫グロブリンファミリーの一員であるTARM1が、2型コラーゲンをリガンドとし、樹状細胞の成熟を促進することで関節炎の発症に重要な役割を果たすことを、マウスを用いた実験で明らかにしたと発表した。この研究は、同大研究推進機構生命医科学研究所の岩倉洋一郎教授、千葉大学真菌医学研究センターの矢部力朗助教、西城忍准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Nature communications」に掲載されている。
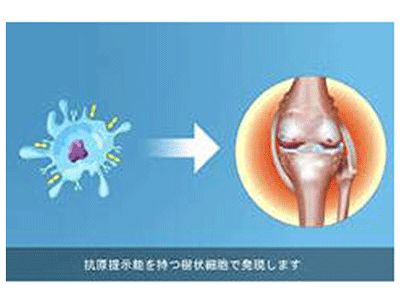
画像はリリースより
関節リウマチの有病率は0.6~1.0%で、日本の患者数は約70万人と推計されている。近年、新たな治療法が開発され、有用性が示されているが、全ての患者に対して効果があるわけではない。そのため、既存薬とは異なる作用機序を持つ新薬の開発が望まれている。
TARM1は最近同定された白血球免疫グロブリン様受容体ファミリーの一員で、細胞外に2つの免疫グロブリン様ドメインと膜貫通ドメインを有する。細胞質側末端には情報伝達に関わる一般的なモチーフは存在しないが、シグナルを入力する際にTARM1は免疫受容活性化チロシンモチーフを持つアダプタータンパク質であるFc受容体ガンマ鎖と会合する。アミノ酸配列解析の結果から、TARM1はOSCARと呼ばれる免疫受容体に近いことがわかっていた。OSCARは線維性コラーゲンの特定のモチーフに結合することで、抗原提示とヒト樹状細胞の活性化、マウス破骨細胞の分化に関わる。
Tarm1遺伝子は、骨髄派生顆粒球、単球、好中球、そして顆粒球マクロファージコロニー刺激因子(GM-CSF)によって分化誘導された樹状細胞で恒常的に発現する。また、TARM1シグナルは炎症に関わるサイトカインである腫瘍壊死因子(TNF)とインターロイキン6のマクロファージと好中球からの産生を増加させることも報告されている。しかし、TARM1が実際に疾患に与える影響はよくわかっていなかった。
TARM1の結合を防止することで樹状細胞の成熟を阻害し、関節炎の発症を抑制
一方、関節リウマチは自己抗原に対する自己免疫反応が、TNFやインターロイキン6、1、17などの炎症性サイトカインの過剰な産生を引き起こし、滑膜の炎症と骨破壊に至るということがわかっている。進行においては、樹状細胞が自己抗原をT細胞に提示し、炎症誘発性サイトカインを産生することによって免疫反応が開始し、増大していく。樹状細胞は、TLRやC型レクチン受容体といったさまざまな自然免疫受容体を発現しており、こうした免疫受容体は樹状細胞の活性化と成熟に重要な役割を果たす。
関節リウマチの発症機序や薬剤の有効性を調べるために、これまで多くの関節リウマチモデルマウスが開発されてきた。コラーゲン誘導関節炎は最も広く活用されているモデルの一つだが、研究グループはこれ以外に、関節リウマチに似た関節炎を自発的に生じるモデルを2種類開発している。これらを用いて関節での遺伝子発現を調べたところ、種々の炎症性サイトカインのほかに、Tarm1の発現が強く亢進していることがわかったという。そして今回、新たに作成したTarm1遺伝子欠損モデルを用いて、自己免疫性の関節炎におけるTARM1の役割を明らかにすることを目的として研究を行った。
その結果、TARM1の発現が関節リウマチモデルマウスで亢進しており、この遺伝子を欠損させたマウスでは関節炎の発症が強く抑制されることを見出した。TARM1欠損マウスでは樹状細胞の抗原提示能が障害され、T細胞の活性化が起きていなかったという。また、2型コラーゲンがTARM1のリガンドであること、2型コラーゲンによって樹状細胞の成熟が促進されることも突き止めた。可溶性のTARM1-FcやTARM1-Flagは、コラーゲンとTARM1の結合を防止することで樹状細胞の成熟を阻害し、関節炎の発症を抑制することも明らかになった。これらの結果から、樹状細胞の成熟においてTARM1が重要な役割を果たしていることが初めて示された。
関節リウマチだけでなく、その他自己免疫疾患、アレルギー疾患の治療標的として有望である可能性
今回の研究成果により、TARM1を介した免疫機能を制御することが、関節リウマチや他の自己免疫疾患、アレルギー疾患の治療に有効である可能性が初めて示された。「有望な標的分子として、今後TARM1に関する研究のさらなる発展が期待される」と、研究グループは述べている。
▼関連リンク
・東京理科大学 プレスリリース




